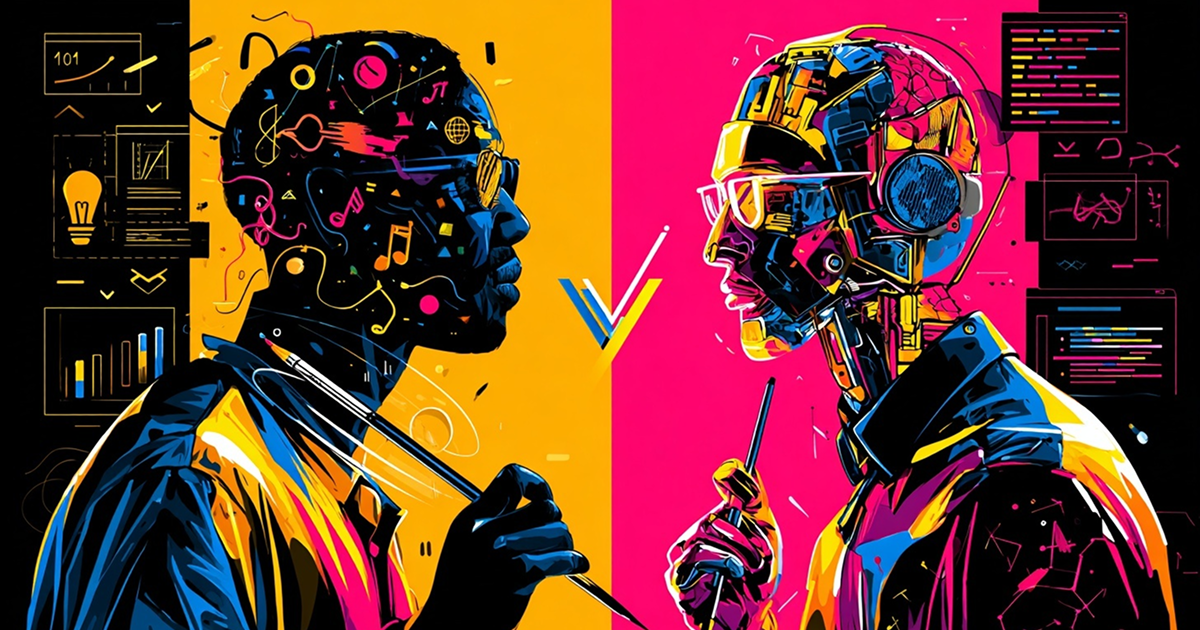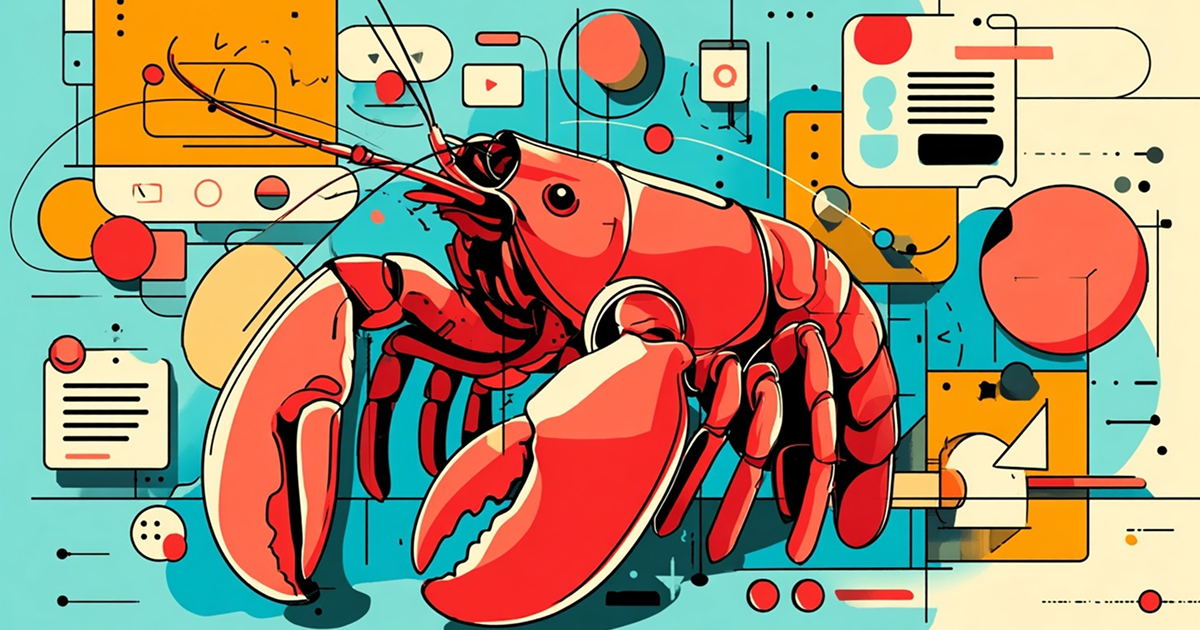ソーシャルメディアでAI生成動画を見ない日はありません。不自然な動物や偽の災害映像が数千の「いいね」を集める一方で、「これでハリウッドは終わり」という声も聞こえてきます。実際の映画業界では何が起きているのでしょうか。映画制作者のブライン・ムーザー氏が立ち上げたAsteria社の事例から、AI動画技術の真の姿が見えてきました。
ARCHETYP Staffingでは現在クリエイターを募集しています。
エンジニア、デザイナー、ディレクター以外に、生成AI人材など幅広い職種を募集していますのでぜひチェックしてみてください!
ボタンから募集中の求人一覧ページに移動できます。
「テキストを打てば映画完成」という幻想

多くの人がSNSで見かけるAI動画を見て、こんな期待を抱いています。「もうすぐAIに『新しいスター・ウォーズを作って』と伝えるだけで、映画が完成する時代が来る」と。しかし映画制作者のムーザー氏は、この考えを明確に否定しています。「シリコンバレーが考えていたテキスト・トゥ・ビデオの形式は、実際には機能しない」と語っているのです。テキスト・トゥ・ビデオとは、文字による指示を入力すると動画が自動生成される技術のことですが、なぜこの方法では映画が作れないのでしょうか。
音楽分野では、AIで歌手の声を真似して楽曲を作ることが既に可能になっています。しかし映像制作は根本的に異なるのです。音楽制作では、メロディーやリズムといった要素をコントロールできれば十分な場合が多いのに対し、映画制作では「ピクセルレベルでの制御」が必要になるとムーザー氏は指摘しています。ピクセルとは画面を構成する最小単位の点のことで、映画制作者は画面の細部まで意図通りにコントロールしたいのです。クリストファー・ノーラン監督のような世界的な映画制作者に「このツールを使って『オデッセイ』をテキストで作ってください」と提案することなど、現実的ではありません。
現在のAI動画技術の最大の問題は、「美的に一貫性がない」ことだとムーザー氏は指摘しています。シーン間での色合いやスタイルが統一されていない、キャラクターの見た目が場面ごとに変わってしまうといった課題があるのです。ムーザー氏によると、これらのツールは「映画を作ったことのない人々によって構築されていた」ことが根本的な問題でした
技術業界は音声AIの成功に影響を受けて映像でも同じことができると考えましたが、人間の視覚は聴覚よりもはるかに敏感で、わずかな不自然さも見抜いてしまいます。では、映画制作におけるAI技術の真の可能性はどこにあるのでしょうか。
実用的なAI活用が生み出す新たな可能性
参照:Cuco YouTube
Asteria社が研究会社Moonvalleyと共同開発したアプローチは、単純なテキスト入力とは全く異なる方法を採用しています。それは現実的で、なおかつ画期的なものでした。
同社では「プロジェクト専用モデル」という手法を使用しています。これは、コア生成モデルのMareyを使用して作品ごとに専用のAIモデルを作成する方法で、オリジナルの視覚素材で訓練された新しいモデルを構築することで、一貫したスタイルを保った映像制作が可能になります。
実際の制作事例として、ミュージシャンCucoのアニメーション短編「A Love Letter to LA」があります(上記動画)。アーティストのポール・フローレス氏が描いた60枚のオリジナルイラストでAsteriaのモデルを訓練し、その結果、同じスタイルを保った新しい2Dアセットを生成して、それらを3Dモデルに変換し動画の架空の町を構築することができました。
Asteria社が他のAI企業と一線を画すのは、「倫理的」なAI開発への取り組みです。同社の生成モデルは、適切にライセンスされた素材のみで訓練されています。DisneyやUniversalがMidjourneyを著作権侵害で訴えた現状を考えると、エンターテインメント業界にとって重要な差別化要因となっているのです。
制作コストについても大きな変化が期待されています。ムーザー氏によると、適切な状況下では1億5000万ドルではなく1000万〜2000万ドル程度で映画制作が可能になる可能性があるといいます。これにより、従来では不可能だった新しい資金調達モデルが実現するかもしれません。
さらに注目すべきは、創作者の権利に関する新しい提案です。従来のPixar映画では、監督や脚本家として参加しても作品の所有権や利益の分配を得ることは稀でしたが、Asteria社では金銭的取り決めによっては、映画制作者が完成後にモデルの部分的所有権を保持できる仕組みを検討しており、収益分配システムの可能性も探っています。
現在、女優のナターシャ・リオン氏が共同脚本・監督する長編映画「Uncanny Valley」の制作が進められています。この実写映画は、現実認識が不安定な十代の少女が世界をビデオゲームのように見え始める物語で、幻想的な視覚要素の多くがAsteriaの社内モデルで作成される予定です。ムーザー氏は「誰もAIの部分について全く考えないでほしい。すべてに監督の人間的タッチが加えられる」と語り、技術と芸術の融合を目指しています。
しかし、この新しいワークフローは制作現場の雇用にどのような影響を与えるのでしょうか。
変化する業界で働く人々の未来

AI技術の導入において避けて通れないのが雇用への影響です。Asteria社が掲げる「より速く、より少ないチーム」での制作は制作効率の向上を意味しますが、同時に雇用機会の減少も意味します。
ムーザー氏は、脚本家や監督がアートディレクターやVFXスーパーバイザーなどの主要な協力者とより密接に作業できるメリットを強調しています。プロジェクトに多くの人が関わるときに起こりがちな修正の行き来に時間を費やす必要がなくなるからです。しかし同時に、これがより少ない雇用機会を意味することも正直に認めています。ただし、ムーザー氏は雇用減少がAI技術だけの問題ではないと指摘しています。VFXハウスのTechnicolor Groupが最近閉鎖されたことを例に挙げ、「生成AIの誇大宣伝が現在の状況に至る前から、エンターテインメント業界の激変は労働者を失業させ始めていた」と述べているのです。2023年にハリウッドを襲った二重ストライキでは、生成AIに関する懸念が大きな要因となりました。脚本家組合と俳優組合の両方が、AI技術による雇用への脅威を交渉の重要な議題として取り上げ、ムーザー氏はこれらの懸念を軽視せず重要な問題であることを認めています。
一方で、ムーザー氏は業界関係者の適応可能性に期待を寄せています。「フィルムでの編集からAvid(デジタル編集システム)での編集に切り替えることができた人々と同じように、この技術に身を委ねたいと思っている映画制作者やVFXアーティストがいる」と語っているのです。特にアートディレクター、撮影監督、脚本家、監督、俳優といった「真の技術者」には、この技術を活用する機会があると考えています。ただし、これは技術を受け入れることに前向きな人々に限った話であることも付け加えています。
重要なのは、業界全体として何が有益で何が危険なのかを理解することだとムーザー氏は強調しています。「ストーリーを語ろうとする私たちにとって何が役立つのか、そして実際に何が危険なのかを知ることが本当に重要だ」という言葉には、技術への期待と同時に慎重さがにじんでいます。
ムーザー氏の取り組みは確かに新しい可能性を示していますが、彼自身が認めているように、その技術と変化が本当に機能するかどうかはこれから証明していく必要があります。映画業界の未来は、技術の可能性と人間の創造性、そして働く人々への配慮のバランスをいかに取るかにかかっているのです。
まとめ

いかがだったでしょうか?
ムーザー氏のAsteria社の取り組みから見えてくるのは、AI技術と人間の創造性が完全に対立するものではなく、適切な形で組み合わせることで新しい可能性を生み出せるということです。しかし同時に、「テキストを打てば映画完成」という単純な未来は現実的ではないことも明らかになりました。技術の限界を理解し、人間の創造性を最大限に活かす方法を見つけることが映画業界の真の課題と言えるでしょう。そして何より重要なのは、この変化が業界で働く人々にとって本当に有益なものになるよう、慎重に進めていくことなのです。
参考記事:Hollywood’s pivot to AI video has a prompting problem
ARCHETYP Staffingではクリエイターを募集しています!
私たちはお客様の課題を解決するweb制作会社です。現在webサイト制作以外にも、動画編集者や生成AI人材など幅広い職種を募集していますのでぜひチェックしてみてください!
また、アーキタイプではスタッフ1人1人が「AI脳を持ったクリエイター集団」としてこれからもクライアントへのサービス向上を図り、事業会社の生成AI利活用の支援及び、業界全体の生成AIリテラシー向上に貢献していきます。
生成AIの活用方法がわからない、セミナーを開催してほしい、業務を効率化させたいなどご相談ベースからお気軽にお問い合わせください!
ボタンから募集中の求人一覧ページに移動できます。